織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など、日本の歴史を語る上で重要な人物をまとめました!偉業や生涯、死因まで紹介。さらに詳しく読みたい場合は、人物ごとのリンクから詳細記事をご覧ください。
※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。
織田信長

織田信長は今から500年近く前、西暦1534年に尾張国(現在の愛知県)に織田信秀の子として生まれました。1582年に没するまでの彼の生涯を、まずは〈若いころ〉〈生涯の偉業〉〈最期〉の三つに分けてご紹介します。
信長の若い頃:「大馬鹿者(大うつけ)」と言われた理由
若い頃の信長に関するエピソードは、「信長のそばに仕えた家臣」の太田牛一が記した『信長公記』という史料に残されています。その書籍によれば、「若いころの信長は風変わりな服装をしていた」とされ、以下のような「見苦しい振る舞い」に関する記述がこの史料に見られるといいます(56〜58ページ)。
町をお通りの時、人目をも御憚りなく、栗・柿は申すに及ばず、瓜をかぶり食いになされ、町中にて立ちながら餅を参り、人に寄り掛かり、人の肩につら下がりてより外は御歩きなく候。そのころは世間公道なる折節にて候間、「大うつけ」とより外に申さず候(町を通る時は、人目も憚らず、栗や柿はもちろん、瓜も齧りつき、町中で立ちながら餅も食べ、人に寄り掛かり、歩く時はその肩にぶら下がってしか歩かなかった。そのころは世の中が礼儀正しい時だったので、「大馬鹿者」としか言われなかった)『信長公記――戦国覇者の一級史料』(和田裕弘著、中央公論新社、2018年)
人目も憚らず、街中で食べ物に齧りついてしまうとはなかなか大胆で、あまつさえ礼儀の正しさが求められる世の中であればこそ、傍目に見て彼が「大馬鹿者」と評されてしまうのは、無理もないかもしれません。
信長生涯の偉業:桶狭間の戦い、室町将軍追放、長篠の戦い
1552年に父・信秀が亡くなった後、信長は織田家を継ぐことになります。1560年には、駿河国(静岡県)、遠江国(静岡県)、三河国(愛知県)で当時勢力を振るっていた武将・今川義元が、尾張国に攻め込んできました。ところが、桶狭間山という小高い丘の上に休んでいた今川軍を、織田軍はわずかな軍勢で襲い、なんと今川義元の首を取ってしまいます。1560年5月19日のこの戦いは「桶狭間の戦い」と呼ばれ、この勝利によって信長の名は全国に知られるようになりました。
1568年には信長は、足利義昭を伴って京にのぼります。この義昭という人物は、父に室町幕府12代将軍、兄に13代将軍をもつ人物でしたが、いとこの義栄が14代将軍となったことに不満を抱いていました。力のある大名を味方に自分が将軍になることを目論んだ義昭は、やがて実際に15代将軍となりますが、信長は将軍の権力を利用して政治の実権を握ります。1573年、戦いで義昭を降参させると信長は義昭を京から追放し、室町幕府を滅ぼしてしまうのです。
また1575年、(後に江戸幕府を開くこととなる)徳川家康が支配していた城が包囲されると家康は信長に助けを求めました。戦場に着くと信長は三重の柵を用意し、戦いでは三列に分けた鉄砲隊を三段構えで配置することで見事、相手方の騎馬軍団を破ることとなりました。この戦いは「長篠の戦い」と呼ばれています。
※以上、本節の内容は主に『織田信長 ――戦国の世をかけぬけた武将――(よんで しらべて 時代がわかる ミネルヴァ日本歴史人物伝)』(小和田哲男監修、西本鶏介文、広瀬克也絵、ミネルヴァ書房、2010年)の22〜25ページの内容を参考にしました。
信長が迎えた最期:本能寺の変
しかし、そんな信長の快進撃も突然の終幕を迎えます。すなわち、それは信長が自害へと追い込まれたためで、この事件は「本能寺の変」と呼ばれています。
1582年、中国地方を支配していた毛利氏を攻めるために備中国(岡山県)に向かっていた信長は途中、京都の本能寺に立ち寄ります。しかしそこで家臣の明智光秀からの裏切りに遭い、ここで自ら命を断つことになるのです(『織田信長 ――戦国の世を駆け抜けた武将――』25ページ)。「光秀が信長を裏切った叛旗を翻した理由については、未だに不明な点が多い」と書かれ、”日本史史上の最大のミステリー”ともされています(渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』筑摩書房、2019年、7ページ)。
「ミステリー」と称されていることからもお分かりのとおり、光秀とこの「本能寺の変」は、これまで多くの論者が取り上げてきた論争的なテーマです。この記事ではこの話題について、これ以上踏み込んだ議論は行いませんが、興味のある方は図書館などで「本能寺の変」について書かれた書籍を繙いてみてください。
豊臣秀吉
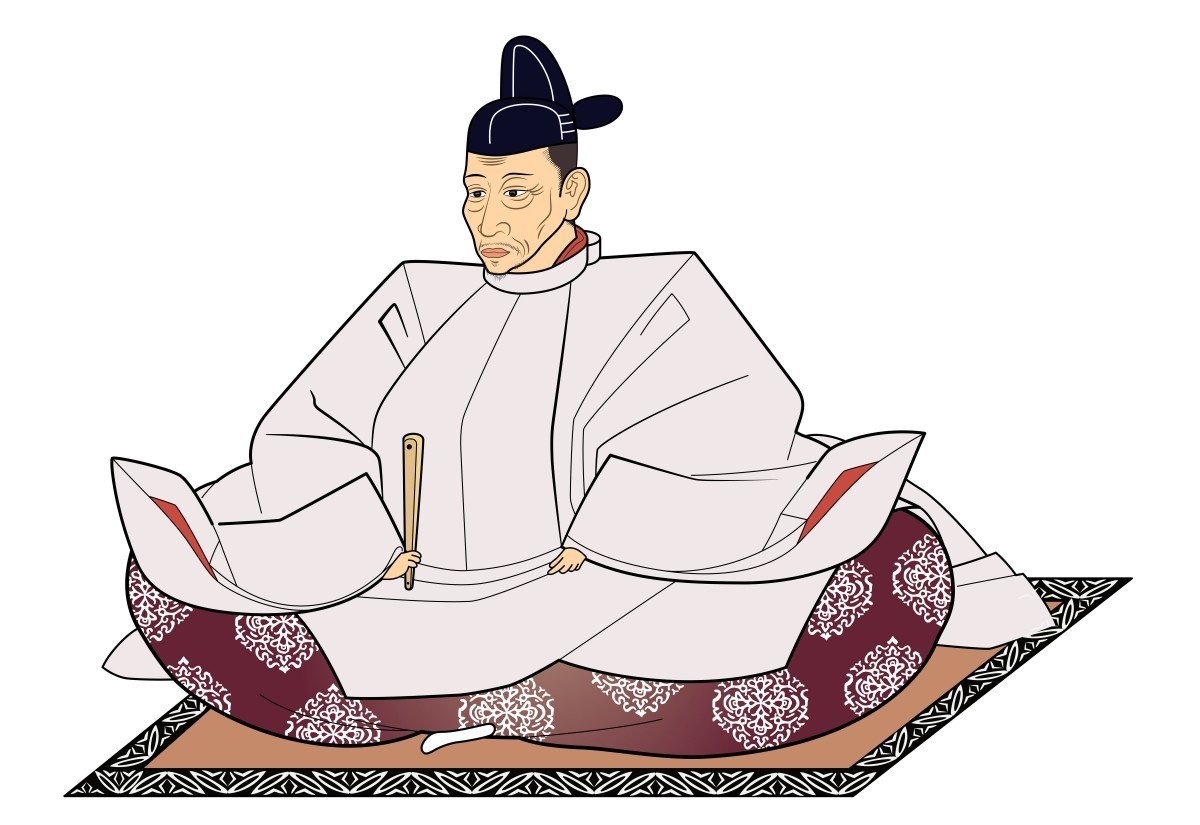
まずは、この豊臣秀吉という人物がたどった生涯を振り返ってみることにしましょう(以下、秀吉の生涯に関する情報は、主に『豊臣秀吉 ――天下統一への道――(よんで しらべて 時代がわかる ミネルヴァ日本歴史人物伝)』(小和田哲男監修、西本鶏介文、青山邦彦絵、ミネルヴァ書房、2010年)を元にしています)。
秀吉の若いころ:放浪、信長との出会い、懐に温めた草履
豊臣秀吉は1537年(1536年とする説も)、尾張国(愛知県)に、農民の子として生まれます。子供のころから、お寺に預けられたり、米屋や鍛冶屋などに小僧として預けられられたりしていたということですが、結局はどれも長続きしませんでした。15歳の頃には木綿針を売り歩いたとも伝えられていますが、やがて生まれ故郷に戻った秀吉は、幼馴染の紹介で織田信長に仕えることとなりました。
秀吉が草履取り(※主人の外出のとき草履をそろえ,替えの草履を持って供をした下僕の意味。参考:『スーパー大辞林』)として信長のもとに仕えていた際の、有名なエピソードに「懐に温めた草履」の話があります。ある冬の寒い日、信長に温かい草履を履いてもらうため、秀吉は信長の草履を懐に入れて温めていました。秀吉が懐で温めていた、この草履を履いた信長は、秀吉がこの草履の上に座っていたのだと思い込んで、叱ってしまいます。しかし事情を聞いたのち信長は、秀吉にすっかり感心してしまい、それから秀吉を「サル」と読んで可愛がることになったというお話です。自分が仕える主人(信長)に気を配り、真心を尽くして信長の心を動かした秀吉はこの後、信長のもとで大躍進を遂げていくこととなります。
豊臣秀吉が成し遂げたこと:天下統一、太閤検地、刀狩令
信長のもとに仕え、戦いでの活躍も認められた秀吉は、仕えはじめてから20年後には「大名」となるまでの躍進を遂げます。1582年に「本能寺の変」で信長が明智光秀の裏切りに遭い、自害に追い込まれると、今度は秀吉が明智光秀を倒し、信長の仇をとります。当時の信長は天下統一(「内乱が終わって一つの大きな国家ができること」 )を目指し、歩んでいる最中でした。信長の後を継いだ秀吉は、1590年に北条氏の小田原城(神奈川県)、奥州(東北地方)を平定して悲願の「天下統一」を成し遂げるのです。
そんな豊臣秀吉が行った政策として有名なものに、「太閤検地」と「刀狩令」 があります。太閤検地とは、1582年から1598年にかけて秀吉が大規模に行った検地、すなわち「土地の広さや米の収穫高を調べる調査」です。広さや収穫高を図る基準がまちまちだったそれまでの検地を改め、計量の基準を全国的に統一することで、収穫できる米の量を正確に調べました。ちなみに、この太閤検地の「太閤」とは、秀吉が呼ばれていた名称を指しています。
また、刀狩令とは、農民から武器を取り上げることを定めた法令です。戦国時代には、兵士として戦うこともあったため、農民たちは武器をもっていました。この「刀狩令」によって、農民から武器を取り上げることで、「武器をもって支配する武士」と「年貢をおさめる農民」の身分がはっきりと区別されることになりました。
👉豊臣秀吉とはどんな性格の人物?その生涯と晩年、名言、死因など
徳川家康

日本の戦国時代、安土桃山時代に戦国武将・織田信長が掲げ、その後を継いだ豊臣秀吉が成し遂げた天下統一(内乱が終わって一つの大きな国家ができること)を目指すプログラムを、江戸幕府を開くという形で完成させ、日本史上類を見ない、平和で安定した時代の礎を築いたのは、この家康でした。この天下統一のプロセスを「餅づくり」に喩えて、こんな俳句が読まれています。
「織田がつき 羽柴がこねし天下餅 すわりしままに 食うは徳川」
※織田信長が餅をつき、ついたその餅を羽柴(豊臣)秀吉がのし、出来立ての餅を何もしなかった徳川家康が座ったまま食べた」という意味
徳川家康の生涯
まずは家康がたどった生涯について、順を追って見ていくことにしましょう。以下、彼の生涯については、『徳川家康 ――江戸幕府をひらいた将軍――(よんで しらべて 時代がわかる ミネルヴァ日本歴史人物伝)』(大石学監修、西本鶏介文、宮嶋友美絵、ミネルヴァ書房、2010年)でまとめられている内容を紹介します。
徳川家康の幼少期から青年時代:他の大名家の人質
徳川家康は1542年、三河国(愛知県)の大名の松平家の長男として、岡崎城で生まれました。当時、この松平家は東を今川家、西を織田家という力のある大名に囲まれていたこともあり、6歳からは織田家、8歳からは今川家の人質として子ども時代を過ごすこととなります。
そんな家康に転機が訪れるのは、19歳の頃のことでした。「桶狭間の戦い」で今川義元が織田信長に敗れると、家康は今川家から離れ、人質生活を終えることとなったのです。こののち1562年の正月には、家康は信長の住まいの清洲城(愛知県)で同盟を結び、1566年には姓を松平から徳川に改めることとなりました。
徳川家康が江戸幕府を開く:豊臣秀吉との争い、関ヶ原の戦い
「天下統一」を目指す織田信長が1582年、「本能寺の変」によって家臣の明智光秀に攻められて自害すると、今度は同じく家臣の羽柴(豊臣)秀吉がこの明智光秀を破り、豊臣秀吉が織田信長の後を引き継ぐこととなります。1584年には、家康と秀吉との間で「小牧・長久手の戦い」が起こっていますが、戦いは決着がつくことなく家康は秀吉と和解、秀吉に従うことを誓いました。1590年には、秀吉に与えられた新しい領地の江戸(現在の東京都)、江戸城へ入ることとなります。
天下統一を果たした秀吉は1598年に亡くなります。秀吉の没後、後継ぎである秀頼を盛り立てて実権を握ろうとする石田三成と家康が敵対すると、1600年には“天下分け目”とも称される「関ヶ原の戦い」が起きます。全国の大名が家康側の「東軍」と三成側の「西軍」に分かれて戦ったこの戦いは、家康側の東軍の勝利に終わりました。
徳川家康の晩年:江戸幕府を開く
関ヶ原で勝利を収めた家康は、1603年に征夷大将軍となって江戸に幕府を開きました。将軍になると、江戸を将軍に相応しい城下町にするため大名たちに号令をかけています。海・湿地の埋め立てが行われ、大名たちの屋敷が江戸城周辺に建てられたことで、江戸は巨大都市へ変貌を遂げました。また1604年からは、東海道などといった道路の全国的な整備を始めました。街道に宿場町を作ったほか、治安を守るための関所で通行人を厳しく調べました。
1605年には、三男の秀忠に将軍職を譲って、家康自身は駿府城(静岡県)で「大御所」としての実権を握ることとなりました。ただ、豊臣秀頼に将軍職を乗っ取られる不安から家康は、1614年の大阪冬の陣、1615年の大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼしています。また、この大阪夏の陣後、「全国の大名は自分のくらしている城をのこし、ほかはとりこわすこと」とした「一国一城令」や、大名たちが守らなければならない決まりの「武家諸法度」など、家康はさまざまな決まりを作っています。
👉『SHOGUN』モデル、徳川家康の生涯と名言。江戸幕府を開いた偉業はいつ?
坂本龍馬

1836年に生まれ、わずか31歳でこの世を去った坂本龍馬の生涯は、短くも波乱に満ちたものでした。現在の四国・高知県にあたる土佐で生まれた龍馬は、家が呉服商や酒造業を営んでいたため比較的裕福であり、10代の頃から剣術を学びました。その後、江戸(現在の東京)でさらに剣術の修行を積みながら、定期的に土佐に戻っていました。
一時期幕府を倒そうとする尊皇攘夷派の一団である土佐勤王党に加わった龍馬はその後江戸に戻り、同様の思想を持つ別の団体に参加しました。映画のような展開ですが、龍馬は幕府の要人である勝海舟の暗殺を企てました。しかし結果的に海舟に世界情勢と海軍の必要性を諭され、その場で弟子となり、やがて神戸海軍塾の塾頭となりました。1866年、龍馬は幕政改革を求める薩摩藩(現在の鹿児島)と急進的な破約攘夷論を奉じる長州藩(現在の山口)の手を結ばせ、薩長同盟を成功させました。
坂本龍馬の死と後世に与えた影響
龍馬は日本の近代化のための8か条の提案(船中八策)をまとめ、その中で政権を天皇に返上することを提唱しました。この提案は将軍・徳川慶喜に提出され、結果として慶喜は1867年に政権を返上しました。この8か条は、明治時代(1868~1912年)の数々の改革の基盤となりました。
しかし、龍馬はその成果を目にすることなく、1867年、自身の誕生日である11月15日に京都の旅館で暗殺されました。犯人は夜8時頃に訪れ、元力士の護衛が背を向けた瞬間に襲いかかり、龍馬とその友人を殺害しました。当初、新選組隊士の大石鍬次郎が犯人として処刑されましたが、元京都見廻組の今井信郎も犯行を自供しました。その他にも薩摩藩黒幕説、新選組犯行説など諸説ありますが、真の犯人が誰であったのかは未だに明らかになっていません。
龍馬の死後、彼の同志であった長州藩、薩摩藩、土佐藩が連合し、幕府側と戦う「戊辰戦争」が勃発しました。この戦争は日本近代史上最大の内戦とも呼ばれ、約1年半で8,000人以上の兵士が命を落としました。最終的に新政府側が勝利し、日本は外国を排除するのではなく、龍馬の提案に基づく近代化の道を選択しました。
近年では、高知県が坂本龍馬を地元の誇るべき偉人として、県の空港を「高知龍馬空港」と命名しました。
安倍晴明

安倍晴明 (921-1005) は平安時代に活躍した陰陽師であり、実在の歴史的存在でありながらさまざまな伝説や物語のモデルになった人物です。主に呪術や占い、天文学を専門とし、「式神」を操る姿が『大鏡』や『今昔物語集』などの古典文学に描かれています。ちなみに式神とは、人の目に見えなかったり、変幻自在に姿を変えたりして陰陽師に仕える鬼神。安倍晴明は、式神を自在に操ることで知られ、呪詛に活用したほか、家の戸締まりなど身の回りのちょっとした処理に利用していたといわれています。
そんな安倍晴明が陰陽寮で天文学や暦学を学生として学んだのは、39歳の頃。そして、陰陽師として『本朝世紀(ほんちょうせいき)』という歴史書に登場するのが46歳。さらに天文博士として貴族が書いた日記に登場するのは51歳のときでした。まさに大器晩成の傑物といえる晴明は、それから84歳で寿命を迎えるまで優れた陰陽師として活躍しました。
長年に渡り精力的に活動した安倍晴明の業績にはさまざまなものがあり、なかでも、占いや邪気を払う逸話がたくさん残されています。そのひとつが、花山天皇の頭痛の原因を前世の頭蓋骨が岩のはざまに落ち挟まっていることだと見抜き、頭蓋骨のある場所まで的中させたこと。その頭蓋骨を取り出し、広い場所に置かれると、花山天皇の頭痛は解消されたといわれています。晩年には、雨乞いの祈祷に成功。天皇から褒美を賜ったことも当時の貴族の日記に記されています。
新選組

「幕末」と呼ばれる時代が始まる起点となったのは、1853(嘉永6)年の「黒船来航」。鎖国していた日本を開国させるため、アメリカからペリーがやってきた事件です。
これをきっかけに、「天皇を敬え」「外国人を追い払え」という尊王攘夷運動が京都で盛んになりました。「天誅」(天の裁き)と言っては、開国に比較的前向きな幕府側の人間を暗殺する事件が増え、京都の治安は悪化の一途をたどります。
これを取り締まるために作られたが、後の新選組。当初は江戸から京都へ向かう14代将軍・徳川家茂(とくがわいえもち)を護衛することを目的に、「浪士組」(「浪士」とは主人を失った武士)という名で広く募集が行われました。
新選組の結成と役割
そこで名乗りを上げたのが近藤勇や土方歳三たち、「天然理心流」の道場のメンバーです。天然理心流は彼らが育った多摩地方(東京都の西側)にある剣法の一派。主流ではないため、“いも剣法”と蔑まれたとか。他にも僧、やくざ、町人など、腕に覚えがある約300人が江戸に集まったそうです。
しかし、浪士組は京都に到着してから分裂。と言うのも、リーダー格にある人物が尊王攘夷の考えを持っていたためです。それと別れて京都に残った近藤勇や土方歳三らを含むグループは、藩主が京都守護職を務める会津藩(現在の福島県会津若松市を中心とする)の預かりとなります。そして、壬生村に屯所を設けて「壬生浪士組」と名乗るように。京都の人々には「壬生浪(みぶろ)」と呼ばれ、恐れられていました。
彼らは1863(文久3)年「八月十八日の政変」(尊王攘夷派を京都から追放するクーデター)で初陣を果たし、功績が認められて朝廷から新選組という名前をもらいます。その本業はあくまで京都の治安を守るための市中見廻り。軍事活動ではなく、警察のような役割を果たす活動でした。
サムライ文化との繋がり
新選組の名を世間に知らしめたのが、1864(元治元)年の「池田屋事件」です。京都を火の海にするという尊王攘夷派による恐ろしい計画があり、これを未然に防ぐことに成功しました。また同年、尊王攘夷派である長州藩(現在の山口県)が武力行使に出た「禁門の変」に参加。この他にもさまざまな働きが認められ、1867(慶応3)年に幕臣(江戸幕府直属の家臣)、つまり武士の身分となったのです。
壬生浪士組の発足以来、組織を維持するにあたり厳守された規則の一つに、「武士道に背くことをしてはいけない」というものがありました。違反した者は切腹をしなければなりません。切腹は自ら腹を切るという勇気が必要な行為であり、武士にとって名誉のある死に方とされていました。
江戸時代は平和が長く続いた時代です。戦いを知らない武士が武士らしくなくなり、その多くが江戸幕府を見捨てていく中、新選組はより武士らしくあろうとしました。彼らは幕府の最期となった「戊辰戦争」まで忠義を通して戦ったのです。それはまさに古き良きサムライ文化でした。
👉「新選組」とは?『銀魂』にも登場する幕末の侍たちを分かりやすく解説
北条時行

2024年7月期から放映されているTVアニメ『逃げ上手の若君』(原作は『週刊少年ジャンプ』連載中の漫画作品)が、にわかに注目を集めています。放映開始直後からSNSで大きく話題となったためご存じの方が多いかもしれませんが、この作品は北条時行(?〜1353 ※1)というひとりの実在人物を主人公とした作品です。※1 本郷和人『北条氏の時代』文藝春秋、2021年、290ページ
日本の歴史に親しんだ人ならば、この「北条」という名字から「きっと時行も鎌倉時代、もしくは戦国時代に活躍した歴史上の人物なのかな」というところまでは連想できるでしょう。しかしきっと、彼が生涯のうちに何を成し遂げたか、というところまで答えるのは難しいはずで、少なくとも「中先代の乱」を起こした……と即答できる人は少ないのでは。
今回の記事では、そんな歴史上の人物としての北条時行について、現在まで伝わる文献などをもとにその生涯を紹介していきます。

Comments