
日本に古くから伝わる日本固有の伝統色がどんな色かご存じですか?その多くは、季節を彩る花や草木、動物などの自然の風景にかかわるもの、行事や旬の食材や食べ物といった文化的なものなどが由来となっています。それらを日本の気候風土によって育まれてきた日本人が独特の色彩感覚により名付けた色が伝統色。
当記事では、代表的な伝統色や歴史に登場する伝統色、季節の色、伝統色が使われているものなどをご紹介します。
日本に古くからある「伝統色」とは?

古くから日本に伝わる伝統色は、四季の違いがはっきりとした日本の気候風土に影響を受けたものや日本文化のなかで生まれたものなどがたくさんあります。
たとえば、花や植物、動物など、うつろいゆく季節や自然の風景に基づくもの、鉱物や半貴石、行事や旬の食べもの、建物や美術、工芸といった文化的なものなど。そのため、伝統色の多くにはその色名になったエピソードがあります。
それも、日本人ならではの感性と色彩感覚のなせる技。その感性と色彩感覚により生まれた伝統色は、長い歴史のなかで織物や染物などの工芸品、建物、日本画などに生かされてきました。今でも着物や和装小物、和紙などに使用され、脈々と受け継がれています。
日本の歴史に登場する伝統色
伝統色は、政治、文化、芸術など、時代を超えてさまざまな場面で登場してきました。ここでは、日本の長い歴史の中で伝統色がどのように登場してきたのか、いくつかのエピソードを紹介します。
冠位十二階:官職の位に応じて決められていた冠の色

冠位十二階は、605年から648年まで行われた官位制度で、官位に応じて冠の色を12色に分け、一目で位がわかるようにしたものです。この官位制度でもっとも位の高い臣下が使える色として指定されたのが、「濃紫(こき)」という濃く深い紫でした。その理由は、紫の染料を抽出するのに手間暇がかかる貴重な染料だったから。そして、2番目の冠位は1番高い冠位の濃紫より染料が少ない「薄紫(うすき)」。3番目以降は、青、赤、黄、白、黒と続き、それぞれが濃淡で分けられていました。
禁色と絶対禁色 :着用してはいけない色があった!?
冠位十二階が廃止されて以降、位による色は冠から衣服の色へと変わっていきました。そして、自分より上位の色の衣服は身に着けることが禁じられることに。その色を禁色といいます。さらに、「絶対禁色」という天皇陛下や皇太子しか身につけられない色もありました。それが、黄色みがかった茶色の「黄櫨染(こうろぜん)」と鮮やかな赤身のある橙色の「黄丹(おうに)」です。
一方、身分の低い人たちが身に着けていた色は、薄い紅色「一斤染(いっこんぞめ)」や「淡い紫色」など。誰でも着用することが許されたため「ゆるし色」といわれました。
時代が進み、江戸時代にたびたび発布されていたのが、華美な色を禁じた「奢侈禁止令(しゃしきんしれい)」。そんなときでも江戸時代の人たちは、許されていた茶色や鼠色からこれまでになかった多くの同系色の色を生み出しました。それらを「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」といい、微妙に違う色を大量に生み出して粋に着物を着こなしていたのです。
平安時代の十二単 :女官のセンスと教養が試される色合わせ

官位や禁色などのルール当然ながら、それとは別に平安時代の女官に必要とされていたのが教養としての色使い。平安時代の宮廷に仕える女官たちが着ていた「十二単(じゅうにひとえ)」は、下の生地が透けて見える裏地のない薄い絹でできた衣を何枚も重ねたものでした。そのため、透けて見える色も含め、色合わせが大切だったのです。
しかも、見映えの良さだけでなく、季節感も重要でした。その基準は、伝統色の名前。伝統色には季節の動植物や風景などの名前が多く、色名と同じ季節に身に着けるのがルールでした。そのルールのなかで組み合わせる色を表現しなくてはならなかったので、センスと教養が必要だったのです。
日本で使われてきた主な伝統色
紫色

冠位十二階でもっとも位の高い臣下の冠の色として定められていた紫。群生する紫草(ムラサキ)の花の美しさが由来となっています。しかし、この紫草の花の色は白。では何が紫色なのかというと、紫草の根を染料として使ったときに染め上げられる色が紫色なのです。この紫草の根を「紫根」といい、染料にするには乾燥させたものを石臼で潰し、袋に入れて湯を注いで漉すといった工程を何度も繰り返さなくてはなりませんでした。しかも、濃い紫色に染めるには染料がたくさん必要なため、濃い紫であればあるほど高貴な印象を与えていたのです。
時代が進み、蘇芳(すおう)という植物からも紫の染料が作られるように。しかし、紫根で染めたものを「本紫」と呼ぶのに対し、こちらは「似紫(にせむらさき)」と呼ばれていました。現在、紫草は絶滅危惧種に指定され、絶やさないよう日本全国で栽培が行われています。
茜色

人類最古の植物を原料とする染料として使われてきた「赤根(アカネ)」という植物を由来にもつ「茜色」。濃く深い赤色で、3世紀頃に日本にあった邪馬台国という国の女王、卑弥呼が中国の「魏」の皇帝から茜染めの布を送られたという記録も残っています。アカネも紫草同様、根に赤い色素を蓄積。この根を乾燥させ煮出したものを染料として使用します。
なお、アカネには西洋茜やインド茜などもありますが、日本茜は根が細いため、染色の材料にするにはかなり多く採取する必要がありました。現在では自生しているものが激減し、希少な染色の材料になっています。
群青色
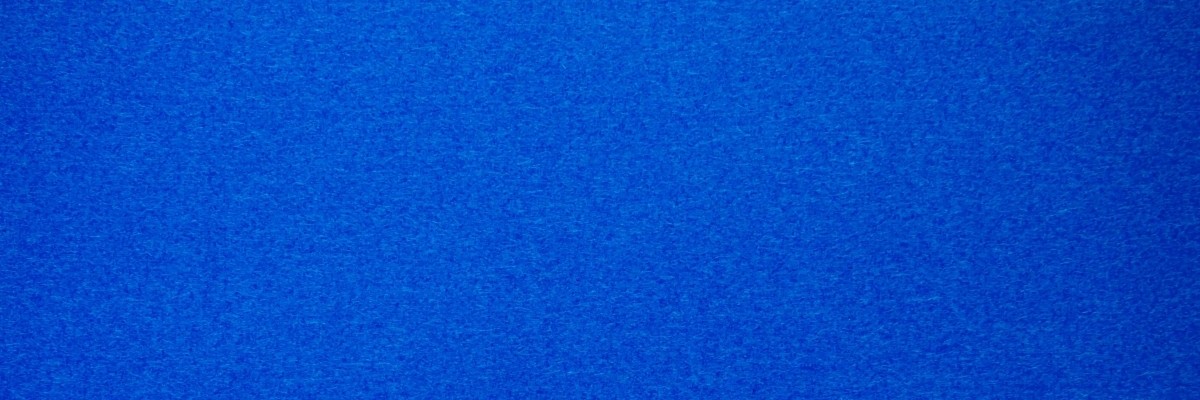
伝統色には染料のほかに、日本画や建築物などの顔料が由来になったものもあります。そのひとつが、紫がかった深い青色の「群青(ぐんじょう)」。藍銅鉱(らんどうこう、英名:アズライト)いう鉱物を砕いて作った、「青が群れ集まる」という意味をもつ岩絵の具「群青(ぐんじょう)」が由来となった伝統色です。
群青は宝石に匹敵するほど高価な顔料だったため、重要な仏教美術にしか使われませんでした。ほかにも青系の伝統色はたくさんあり、茜色と並ぶ人類最古の植物染料の「藍色」も青系の伝統色のひとつです。
日本の季節にちなんだ伝統色
春:桜色

桜色とは、平安時代に誕生した薄い紅色です。当時は桜といえば山桜でした。しかし、山桜の花の色は白。なぜ薄い紅色が桜色と名付けられたのかは、着物の色彩の「かさね色目(いろめ)」のルールをみればわかります。当時の絹は薄く透けて見える布で、裏地の色が透けて見える特性を生かし、色を重ねて季節を表現していました。春だけでもさまざまなパターンがありましたが、そのひとつが桜。「表地に白、裏地に赤花」という色を合わせて山桜を表現したのです。
夏:撫子色

撫子色とは、平安時代に生まれた撫子の花のように紫がかった薄い赤色です。「かさね色目」としては「表地が紅、裏地が紫」または「表地が紅梅、裏地が青」、「表地が蘇芳、裏地が青」など諸説あります。古くから日本の女性の美徳とされた、おしとやかで美しい女性を表す「大和撫子」の語源となった花で、伝統色としても「かさね色目」としても美しい色です。
秋:紅葉色

紅葉色は、晩秋に色づく楓の葉のような鮮やかな赤色です。由来は、平安時代の装束の重ねの色目。「表地が赤、裏地が濃赤」で赤く色づいた楓の葉が重なっている様子が表現されています。紅葉色の重ねの色目も諸説あり、そのひとつが「表地が黄色、裏地が蘇芳」。こちらは黄色に色づく葉と赤く色づく葉を表現。平安時代に生きた人たちの色彩感覚が感じられます。
冬:銀鼠 (ぎんねず)
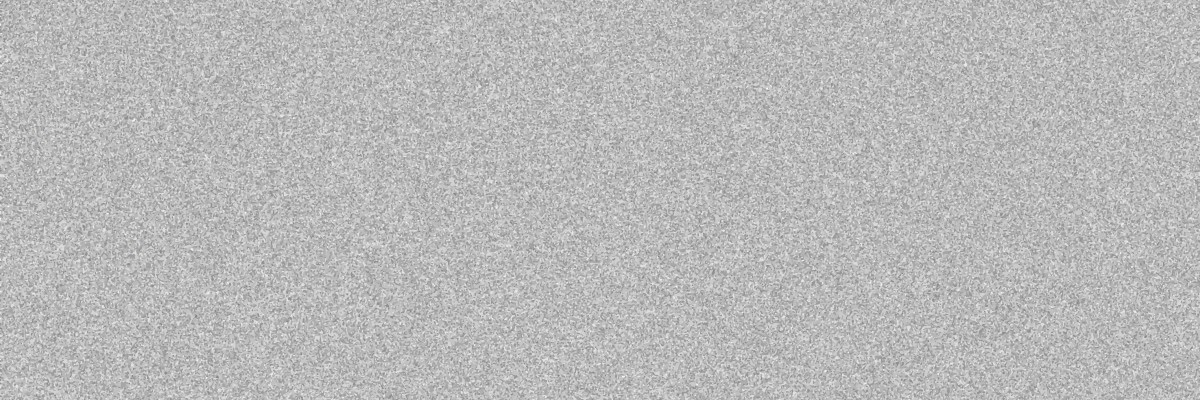
銀鼠色は銀色がかった明るい灰色で、奢侈禁止令が発布された際に流行した「四十八茶百鼠」のひとつ。また、濃墨、焦墨、重墨、淡墨、清墨といったグラデーションで描かれる水墨画の「墨の五彩」の淡にあたる色でもあり、顔料としても使われてきた伝統色です。
伝統色が使われている、日本の小物や雑貨
現在でも伝統色が使われている代表的なものが着物や帯、着物を着る際に必要な帯揚げや帯締めなどの和装小物。そのほか、日本人形や和紙、折り紙 、スカーフなどにも伝統色が使われています。伝統色のなかには縁起の良いものもあるので、お土産を選ぶ際は伝統色の名前も参考にしてみては?




Comments